NEWS新着情報
平和体験企画『沖縄』行ってきました!!
平和企画 2025/04/23
3月29日(土)~31日(月)に、小学生から大人まで19名の組合員さんと一緒に沖縄へ行ってきました

【一日目】
早朝に中部国際空港を出発し那覇空港へ到着後、今回ガイドをお願いした横田眞理子さんと共にバスにて平和記念公園へ向かいました

空港を出発したバスが通る道沿いにも広々とした基地が広がっていました



テレビのニュースでよく目にする『平和の礎』(へいわのいしじ)。

沖縄戦で犠牲になられた方々の氏名がびっしり刻印されていますが、横田さんからの解説で、その一部の方の犠牲になられた経緯を知り、他のあまりにもたくさんの方々一人一人にもそれぞれの状況があったことに思いめぐらせました。
激しい沖縄戦の後、数えきれない遺骨を生き残った人たちが集めて慰霊した『魂魄の塔』(こんぱくのとう)。


夏の『千羽鶴を作ろう』『千羽鶴作り&交流会』企画で組合員さんがまとめてくれた千羽鶴を奉納しました。




『魂魄の塔』から茂みの中を少し歩いて『米須海岸』(こめすかいがん)へ。
沖縄本島の南端の浜の一つで、足元はサンゴ礁からできたゴツゴツした岩が多い所ですが湧き水があったことから、米軍の目を盗んでたくさんの人が水を汲みにきたそうです。
この後、動員され日本軍の支配下におかれ沖縄戦で犠牲になった227名もの女学生たちを慰霊する『ひめゆりの塔』『ひめゆり平和祈念資料館』を見学して回った後、バスにて那覇のホテルに向かい、夜は交流会を行いお互いに一日目に感じたことなどを語り合いました。


【二日目】
バスにて南風原病院壕(はえばるびょういんごう)へ。
戦局の悪化に伴って1944年5月に編成された沖縄陸軍病院は10月10日の「10.10空襲」にて施設が焼失し、南風原(はえばる)国民学校校舎へ移転。その後、近くの小金森(標高85m)周辺に約30の横穴壕が造られ、米軍の激しい艦砲射撃が始まった1945年3月下旬に陸軍病院はさらに各壕へ移転しました。
そのうちの一つである『南風原病院壕20号』へ。




暗く粗末で換気の悪い壕の中で重傷者の手当てや手術が行われ、動員されたひめゆりの女学生たちが看護や食事、排せつの世話に翻弄されていたことに思いを巡らせました。


陸軍病院の炊事に使用された井戸は壕と離れていて、ひめゆりの女学生たちは米軍の攻撃をかいくぐってこの『めしあげの道』をおよそ10kgもある食料や水の入ったタルを運んだということでした。今では木々が茂った山道に見えますが、爆撃を受けていた当時は身を隠す物が何もない、ただのはげ山だったということです。
この後、バスで北へ向かい、米軍基地のキャンプハンセン、キャンプシュワブを通って、今着々と埋め立て工事が行われている辺野古基地を対岸から望み、沖縄の置かれている現状を目の当たりにしました。
次の目的地である嘉手納へ向かう高速道路入り口のY字路は、右に進むと高速道路入り口、左に進むと米軍基地入り口、となっていて、間違って入ってしまう程『米軍基地』が身近であることを実感しました。
「道の駅かでな」から眼前に広がる嘉手納基地(かでなきち)を眺める。

見えているのは嘉手納飛行場のほんの一部で、他に嘉手納弾薬庫地区、陸軍貯油施設があります。戦前に日本陸軍の飛行場が建設されたことから米軍の上陸地点となり、集中砲火によって町の全てが破壊され、戦後は米軍の管理となり、朝鮮戦争では「極東最大の空軍基地」として重要視、拡張されて、今では町の82%が基地になっています。
航空写真を見るとほんの一部の区画に住宅が密集している様が見て取れ、町としてのあり方やここで暮らす人たちの暮らしがどういうものなのだろうか、と考えずにはいられませんでした。
嘉手納基地からほど近くの北谷町(ちゃたんちょう)の米軍上陸地、砂辺海岸(すなべかいがん)に降り立つ。




1945年4月1日に、米軍の戦艦、駆逐艦、砲艦など合計219隻が海面を覆いつくして激しい艦砲射撃の後、上陸した所です。
小雨の降るなか穏やかな灰色の海を見渡しても、米軍の船が海面を黒く埋め尽くした不穏な様を想像するのは難しいことでした。
砂辺地区には、米軍関係者が住む基地外住宅も多くあり、米軍ナンバーの車もたくさん見かけました。基地というのは、そこに基地があるだけでなく、すぐ隣に米軍関係者が生活しているということに気づかされました。また、住宅地のそこここに数本の木が茂った緑の敷地があります。これは騒音に耐え兼ね補償をもらって住民が立ち退いた跡とのことで、地域が成り立たなくなっていくのではないかと感じました。
宜野湾市(ぎのわんし)にある嘉数高台(かかずたかだい)へ。




あいにくの雨の中でしたが、嘉数高台から普天間基地を望むとオスプレイが駐機しているのがわかりました。
嘉数高台(かかずたかだい)にある『トーチカ跡』。






ここは日本軍が陣地を築いていた場所で、「トーチカ」とは鉄筋コンクリート製の箱のようなもので、中に兵士が入って開口部から銃で反撃するようになっています。
コンクリートの崩れ具合から砲撃の激しさが伝わってきました。
【三日目】
沖縄のモノレール、ゆいレールに乗って、対馬丸記念館(つしままるきねんかん)を見学。


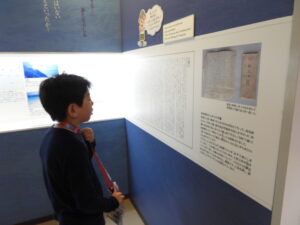
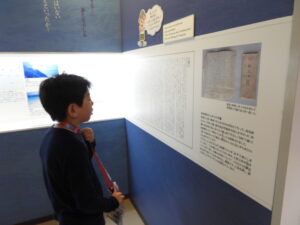
1944年戦況の悪化に伴い、沖縄では老人、幼児、婦女子は県外への疎開が指示され、学童集団疎開の子どもたちを乗せ8月21日に那覇港を出港した対馬丸は翌日の夜、米軍の潜水艦の魚雷攻撃により海に沈められ乗船者1788名のうち約8割の人々が犠牲になったということです。
見学の後、10歳の時に沖縄戦を経験された玉木利枝子さんからお話していただきました。






小学校4年生だった玉木さんは、祖父の反対で対馬丸へは乗らず、10.10空襲で那覇の家が焼け、父親の入隊後、死ぬ時は家族一緒に死にたいと軍隊を探して南へ移動したそうです。その間、家族と一緒に自然のガマに何日も隠れていたり、軍隊から「このガマは軍隊が使うから出ていけ」と言われ、入れる壕を探し歩いたことや、光が目の前を通り過ぎたと感じたら同年の男の子が死んでいた。他にも兄が目の前を通り過ぎたと思ったら血染めの腕をかかえていて野戦病院で腕を切り離され板に乗せられ「水を欲しい」と言いながら息を引き取った姿を今も鮮明に覚えていることや、気がふれた軍人、祖父の死、祖母の死、動けない叔母に「逃げろ」と言われて一人歩きだしたこと、軍属の男の人、女の人、子どもの3人に仲間に入れてもらい一緒にいた、とにかく「死ぬときは一気に死なせてください」と祈っていたこと、ある日真昼間なのに砲弾が落ちてこないことを不気味に思っていたら戦争が終わっていたとわかった、などを話してくださりました。
戦後50年までずっと話さなかった、「戦後生まれのいとこたちに、こんな身内がいたと知らせなくてはいけない」と思い文章にし、75歳の時にどうしてもと頼まれて話し始めたとのことです。
家族をことごとく失って、生きてきた玉木さんの言葉です。
「人間は生きてさえいればいろんなことができる。」
「どんなことがあっても生きる。命を守る。」


最近の記事
2026年2月25日
【農業体験】たまねぎを植えてみた!…2026年2月24日
おしゃべりひろば 3月 開催予定…2026年2月19日
平和体験企画 広島2泊3日 事前交流会…2026年2月18日
生産者に会いに行こう!~生産者交流会~…2026年2月17日
ライフプランニング学習会…

